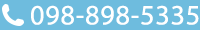土木業界の今後は?現状の課題から解決策まで徹底解説
2025年03月11日 |

土木業界にお勤めの皆さま、「土木業界はこれからどうなっていくのか」という疑問を持ったことはありませんか?
土木業界は戦後の高度経済成長期から日本のインフラ整備を支え、安全で住みやすい生活基盤を築いてきました。
しかし現在、業界は慢性的な労働力不足と高齢化という深刻な課題に直面しています。
さらに、インフラの老朽化やデジタル技術の遅れなど、多くの課題が山積しており、急速な変革が求められています。
一方で、業界の市場規模は堅調に成長を続け、約25兆4,500億円に達しています。
日本は自然災害が多く、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が進んでいることから、土木業界の需要は今後も拡大していくと予測されます。
そこで本記事では、土木業界の現状を分析し、直面する課題を明らかにするとともに、新たなビジネスチャンスや技術革新がもたらすメリットについて解説します。
土木業界に携わる皆さまには、ぜひ参考にしていただければと思います。
土土木業界が抱える課題
土木業界は労働力不足や従業員の高齢化など、様々な課題を抱えています。
ここでは、多岐に渡る課題を整理し、それぞれの詳細について解説します。
高齢化
現代の日本は少子高齢社会であり、どこの業界でも高齢化が進んでいますが、土木を含めた建設業は特に顕著です。
国土交通省のレポートによると、建設業(土木・建築)の現場従事者のうち、約3割が55歳以上となっています。
土木業界における高齢化は、主に二つの課題をもたらします。一つは後述する人手不足(労働力不足)の問題、もう一つは高齢技能労働者の技術継承の問題です。
前述のように、現場従事者の約3割が55歳以上であることから、これらの人材は今後数年以内に退職することが予想されます。
若手の採用が困難な現状では、さらなる労働力不足につながることは避けられません。
技術継承の問題も深刻です。土木技術は専門的な知識と技術、豊富な経験を必要とするため、熟練技術者の高齢化に伴い技術の継承が途絶えることは、業界にとって重大な損失となりかねません。
出典:建設業を巡る現状と課題
労働力不足
土木業界は深刻な人手不足問題を抱えています。
前述した人材の高齢化によって、数年以内に退職が見込まれること、そして若い人材の確保が難しいことにより、慢性的な労働力不足に陥っています。
厚生労働省の令和6年上半期雇用動向調査によると、建設業全体の入職率は7.5%となっており、業界に入る人材が少ないことを示しています。
また、離職率は6.3%と全産業の離職率8.4%と比較してそう高い数値ではありません。
しかし、新規高卒者の3年以内の離職率が42.4%と高くなっていることから、若手労働者の中でもより若年層が早期離職に繋がっている可能性があります。
離職の原因には「労働環境の厳しさ」、「賃金の低さ」等が考えられ、現状の労働者不足を解消するには、早急にこれらの課題に取り組む必要があります。
出典:新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します|厚生労働省
廃業の増加
2024年に倒産した建設業は1,890件に上り、過去10年で最多を更新しています。
上記にあげた高齢化や労働力不足、そして資材価格の高騰等の理由により、倒産及び廃業する事業所が増加しているのです。
特に、資材価格やエネルギー価格等の物価高による倒産が全体の1割を占めているとのことで、多くの企業が経営困難に直面しています。
インフラの老朽化
高度経済成長期以後に建設されたインフラ設備の老朽化が止まりません。
近年、道路の陥没や水道管の損傷といった形で具体的な被害が発生し始めています。
国土交通省によれば、今後20年間で築50年を超えるインフラ設備が加速度的に増加していくことが言及されています。
このまま対策が遅れれば、インフラ事故と規模が拡大し、私たちの安全な生活が脅かされることになります。
一方で、やはり人材不足という課題によってその整備が追い付かないという懸念があり、作業の効率化や省力化が不可欠です。
デジタル技術活用の遅れ
上記のような課題を解決する手段としては、デジタル技術を活用した業務改善が課題解決に繋がります。
では、土木業界のデジタル技術活用状況はどうなっているのでしょうか?
2021年の総務省の調査によると、建設業でDXに取り組んでいると回答した企業は全体の20%程度であり、今後も実施する予定がないと回答した企業はなんと60%にも上ります。
そのため、取り組みの進捗状況はあまりよくありません。
参考:総務省「デジタル・トランスフォーメーションによる経済へのインパクトに関する調査研究」
土木の未来を支える技術革新と課題解決策
労働力不足やインフラ老朽化の課題を解決するには、労働者・担い手の確保、生産性の向上が求められます。
それらを実現するために、具体的にどのような解決策が必要なのか、以下で解説していきます。
働き方改革と人材確保の施策
2024年1月より、建設業では時間外労働の上限規制が適用されるため、今後は残業が発生しないよう、効率的に業務を実施していく必要があります。
そのため、デジタルシステムや技術に投資をしていくことが効果的です。
後に解説しますが、DX(デジタルトランスフォーメーション)の考えをもとに業務改革を行っていくことで、生産性が上がって労働時間が減り、残業の抑制に繋がります。
また、CCUS(建設キャリアアップシステム)を活用した処遇の改善も有効です。
CCUSは、建設業に従事する技能者の資格や経験をデータベース化し、適正な評価や処遇の向上を図るためのシステムです。 CCUSによって、キャリアの可視化や技術者のスキルを適正に把握することができ、経験や能力がに評価され、賃金の向上や安定した雇用につながります。
DXの推進
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がAI、IoT、ビッグデータなどのデジタル技術を活用して、業務効率化や新たなビジネスモデルの創出を目指す取り組みを指します。
土木業界におけるDXの導入は、業務の効率化に寄与するだけでなく、労働環境の改善や安全性の向上にもつながります。
以下に、具体的なDXの活用事例を紹介します。
BIM/CIMの導入
BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)は、設計・施工・維持管理の各段階において3Dデータを活用する技術です。
3Dモデルを用いることで、関係者間の情報共有をが簡単にできるようになり、ミスや手戻りの削減、作業負担の軽減、工程短縮を実現し、安全性や経済効果の向上につながります。さらに、インフラの質の向上や建設業従事者のモチベーション向上にも寄与することが期待されています。
基幹システムの導入や業務システムの導入
土木の業務は、計画・設計・測量・施工・維持管理といった業務プロセスとなっています。
それぞれのプロセスで業務効率化につながるシステムを導入することで、生産性アップが期待できます。
例えば、積算システムの導入や安全管理の効率化につながるシステムを導入し、業務時間を短縮することで、人材不足等の課題に貢献することができます。
また、これらのシステムは属人化の防止や外国人労働者への対応、入札への強み等を期待できます。その結果、高齢化の課題解決や売上向上等の成果にもつながります。
ICTの活用
土木工事におけるICTの活用とは、従来の紙媒体の図面や人力中心の作業から、デジタル技術を駆使した設計、施工、管理へと移行し、生産性向上を目指すものです。
例えば、ICT建設機械を活用することで、まだ経験が浅いオペレーターでも品質の高い施工が可能になったり、安全性の向上、作業の効率化を実現することが可能です。
他にもドローンを活用した3次元測量や3次元設計データでの施工計画の作成など、様々な業務プロセスで活用することができます。
まとめ:未来の土木業界の展望
今回は土木業界が抱える課題について整理し、その解決策について紹介しました。
人手不足や高齢化といった人的資本に課題を持つ土木業界ですが、様々なデジタル技術が活用されるようになり、大きなビジネスチャンスと捉えることもできます。
現在はICTをはじめとしたDX化が進んでおり、近い将来デジタル技術が用いられての設計や施工が当たり前の時代が来ることでしょう。
その波に取り残されないよう、業界の課題とその解決策についてしっかりと理解しておくことが大切です。